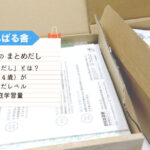こんにちは、とはのです。
皆さんのご家庭では、家庭学習をしていますか?
また、その際に通信をご利用されていますか?
今回は小学校1年向き、もしくは来年度小学校に上がる年長のご家庭向きの内容で、テーマは「Z会の小学1年生・ハイレベルコース」について。
今回紹介すること
- Z会1年生・ハイレベルコースを一年受講した感想
難易度や問題について(Z会って評判だけど実際どうだったか) - Z会のけいけん学習について
- Z会をおすすめしたい人、あっていると思う人
私の子供はZ会の小学校1年生・ハイレベルコース(紙教材)・みらい思考力ワークを受講しました。
その経験をもとに、上記のことを感想(備忘録・ブログ)も兼ねてお伝えします。
小学校からZ会を始めようとしている人、家庭学習が気になる方はご参考ください。
2023.2追記
ちなみに2023年度(2023年4月)から、新小学1年生と新小学2年生のコース選択(スタンダード・ハイレベルコース)はなくなりました。
コース選択なし、1コースのみだそうです。2023年2月に電話で問い合わせたところ、そのように回答いただきました。
レベル的もスタンダードよりもハイレベルコースに近いかも、といった回答だったように思います(電話先の相手もハッキリした回答ではなかったので、気になる方はお問い合わせくださいね)
以下はコース選択があった当時の話なので、その点ご了承ください。
-

-
Z会はいつから?お子さんの習熟度別おすすめ入会時期|小学生編/ブログ
こんにちは、とはのです。 Z会について、以前小学1年生の総評をお伝えしました。 その後、Z会を始めるならいつからがおすすめかといった質問がきたので、それにお答え ...
続きを見る
Z会の小学1年生:こくご・さんすうの難易度と問題
通信について調べていなくても、名前は知っている人が多い「Z会」。
実際に小学1年生の子供が続けてどうだったのか。
まずは難易度や問題について、一年をとおした感想をお伝えします。
(下記、見たい項目の「+」ボタンを押すと情報が表れます)
一年間の総評
Z会は後半になるにつれ、Z会らしさ・こちらが求めるものが表れてきたと感じました。
ただ、前半はそれが伝わりづらいので、その段階でZ会を離れてしまう人もいるかもしれません。
Z会の資料請求をすると、おためしとして3分の1~半月分の問題をもらえます。目安としてそれを見て、難易度を測るのも良いかもしれません。ついでにおためし教材には保護者用の回答冊子も付いてくるので、Z会の解説が手厚いのもわかると思います。
懸念点として、資料請求時にもらえるおためし教材は4月(前半期)の難易度に合わせているかもしれないということ。実際に入る月の難易度と多少異なっている可能性があることを、留意しておくと良いですね。
Z会の1年けいけん問題について

Z会の特徴として、毎月、経験学習の「けいけん」問題がついていることです。
「けいけん」は理科や社会につながるテーマで、実体験をする教材。自然や社会に関心をもつことをねらいとしています。
たとえば、アイスクリームを作ったり、シャボン玉を作ったり、街なかの標識を探したり。
こうしたテーマが毎月与えられていて、そのために必要な準備・実践・理解をします。
終えたあとは、「けいけんシート」というところに絵と、なにを表現した絵か、なにが楽しかったかを書いて提出をします。
「けいけん」は(親が)面倒だが、(子供の)記憶に残る
ひとつの「けいけん」に対してかかる時間は、大体2~3時間。子供がひとりでできるわけではないので、親子で一緒に取り組みます。
テーマによっては準備するものもたくさんあって、親がけっこう大変&面倒だと思うことも。
反面、子供にとっては楽しい取り組みだと感じるでしょう。親と一緒にするならなおさらです。
そうした「楽しい」という思いと、経験したことが結びつくと、記憶にも残りやすいのではと思います。
経験する場が減っている現代の子供にきっかけを与える
季節の植物や虫に興味を持ったり、調べたり。
アイスクリームを作ったり、磁石で遊んでみたり。
自分でシャボン玉を作ってみたり、もち米からお餅を作ってみたり。
これらを子供のころ経験した親はいるかもしれませんが、お子さんは経験されていますか?
現代の子供はあまり経験していないのでは。アイスもシャボン玉も買うことが当たり前になってきているし、簡単なおもちゃなら作るより100均で買ったほうが早いです。
庭が無い家も多く自然に触れる子供も減ってきました。
Z会の「けいけん」問題は、昔と違い経験をすることが減っている子供たちに、そうした場を提供するきっかけになっているのかもしれません。
Z会の「けいけん」のように、子供と実験や遊びをとおしてして学ぶ書籍は多くあります。
もしもそれらをお持ちで、すでに取り組んでいるのであれば、とくに必須ではないかもしれません。
ただこうした取り組みをされていないご家庭であれば、「けいけん」ワークはおすすめです。
Z会をおすすめしたい人、あっていると思う人
あくまで小学校1年生のZ会についてですが
- 基盤(学校の教科書)をおろそかにしない。学習習慣や読み書きの土台形成をしっかりさせたい人
- 無理にステップアップはしない。着実にレベルを上げていきたい人
- シンプルな教材を求めている人
などを求めている人であれば、あっているかと思います。
基盤(学校の教科書)をおろそかしない。学習習慣や読み書きの土台形成をしっかりさせたい人
前述したとおり、1年生のZ会は教科書レベルの内容をベースとしたうえで、身につけておいたほうが良いと思われる発展事項をプラスした教材です。
学習習慣や読み書きの土台形成ともいえる時期で、その部分をおろそかにしていると、後で歪みが起きてしまう可能性もあります。
とくに小学校1年生の前半部分は、家や学校での学習習慣がまだ身についていない、学校での勉強もすこしあやういかもしれない、そんなお子さんでもついていけるようなレベル設定になっています。
無理にステップアップはしない。着実にレベルを上げていきたい人
1年生の前半は問題がやさしいものの、後半からは徐々にレベルを上げていきます。
それでもしっかりとした解説やヒントが書かれているので、急激なレベルの変化・無理なステップアップを感じるお子さんは少ないでしょう。
しかし、Z会での難しい問題は、市販の難しい問題集と比べると難易度がやさしいはずです。
すでに市販の難しい問題集で満足しているご家庭であれば、Z会の難易度はあわないと思うので無理して入会されなくても良いでしょう。
シンプルな教材を求めている人
Z会はシンプルな教材です。
解説する先生などのイラストはありますが、子供が惹かれるようなキャラクターはいませんし、紙教材以外の付録もありません。
逆にそのほうが子供の気が散らないし良い、集中できるというご家庭であればあっています。
2年生でもZ会・ハイレベルを受講
最初は値段の割にいまいちかも?と思ってしまったZ会ですが、わが家では2年生でも採用しました。
- 1年生の後半期の良問の数
- 自然とステップアップさせる仕組みがある
- 2年生は1年生と比べて学習量(問題)が増えている
- 紙教材を使いたい
- 来年度(3年生)の受験コースも視野にいれるため
こうした理由で決めたZ会2年生。
1年生ではZ会を受講するのが初めてでいろいろモヤモヤしましたが、2年生は納得して進められました。
またなにかの折にお伝えする予定ですが、2年生は1年生よりレベルが高い問題・考えさせる問題の出題率が上がっています。
小学校受験組、サピックス・ハイレベ教材を普通に使用している人であれば、かんたんかもしれないので、3年生の中学受験コースから。
普通の家庭学習・通信レベルであれば、2年生から。家庭学習をしたことがない人は、1年から受講することをおすすめします。
Z会 公式HP(各学年のワーク内容もサンプルとしてすこし確認できます)
-

-
Z会はいつから?お子さんの習熟度別おすすめ入会時期|小学生編/ブログ
こんにちは、とはのです。 Z会について、以前小学1年生の総評をお伝えしました。 その後、Z会を始めるならいつからがおすすめかといった質問がきたので、それにお答え ...
続きを見る
-

-
小学2年からZ会はじわじわくる。国語はハイレベ100よりも上か
こんにちは、とはのです。 今回はZ会の小学2年・ハイレベルコースを中心にお伝えします。 Z会の小学1年は大したことがないように思ったが、小学2年はどう? Z会を ...
続きを見る
-

-
小学2年生【Z会ハイレベル】1年間のカリキュラム内容と感想
こんにちは、とはのです。 今回は小学2年生が取り組んでいたZ会(小学生コース・ハイレベル)について、1年間の振り返りをしたいと思います。 Z会・小学2年生で利用 ...
続きを見る