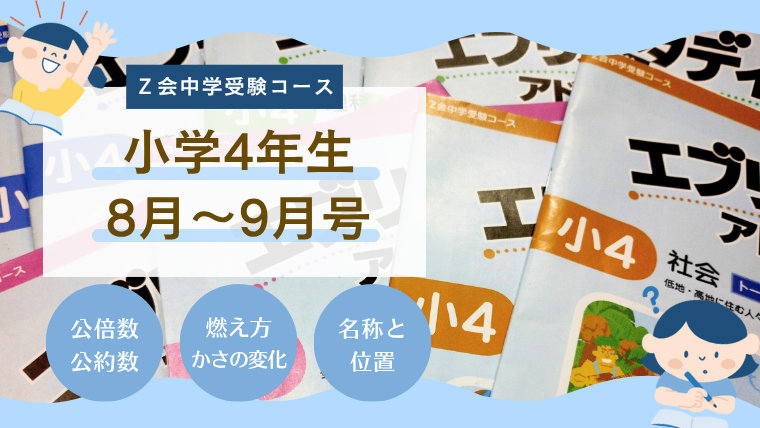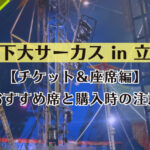こんにちは、とはのです。
今回はZ会の中学受験コース・小学4年生の8月号・9月号についてササッとまとめてみました。
Z会の内容は毎年微妙に変わっているところもあるので、あくまで「ある年の例」としてご参考ください。
-

-
Z会中学受験コース・小学4年生6~7月号/社会は漢字に苦戦?
こんにちは、とはのです。 今回はZ会の中学受験コース・小学4年生の6月号・7月号についてです。 すこし駆け足記事ですが、気になる方はご参考ください。 過去のZ会 ...
続きを見る
過去のZ会の記事は、「Z会の記事一覧」をご確認ください。
国語/8月は人物の行動と性格、9月は言葉がテーマ|小4・Z会の中学受験コース
8月号の国語は登場人物を読み解く/小4・国語
8月号の国語では、登場人物がどんな性格なのか読み解く練習をおこないました。
授業ノート(テーマの解説&練習ページ)では、読み取り方の方法や、数行の文章を読んで、それぞれの登場人物の性格はどういうものかを自分の言葉で書きます。
文章題は心情を問うものが多いので、最初テーマを見たときは「今さらなぜこれがテーマに?」との印象を受けましたが、テーマにすることで意識を高めることにもつながるのかもしれません。
問われたときに初めて、なんとなく感じたことをどう表現すればよいか悩み、必要に応じて読み直すこともあると思います。
しかし、それをテストでやってしまうと時間のロスに繋がるため、最初からある程度登場人物の立場や感情、性格を意識しながら読むクセをつける必要があるのかなと感じました。
漢字は都道府県が中心
8月号の漢字学習は、都道府県で使用するものが中心でした。
都道府県でしか使わない漢字が多く、かつ形が難しいものが多いです。
学校でも漢字のテストはもちろんのこと、社会でも都道府県に関することを調べたり覚えたりするので、漢字は早めにマスターしておくと良いかもしれません。
9月号の国語は「言葉について考えよう」/小4・国語
9月号のテーマは「言葉について考えよう」でした。
文章題で言語を取り扱ったものがそろっていたので、その影響でテーマを「言葉について考えよう」にしたのかもしれません。
「練習ノート」では話し言葉や文字、手話、方言や共通語などがあることを解説し、次にすこし難しい言葉や類義語・対義語などを軽く説明していましたが、内容はやや薄く感じました。
構成上、「練習ノート・漢字練習・文章題」にしているので、練習ノートの項目を抜かすわけにもいかず、無理に内容を入れ込んだ印象を受けます。
算数/8月は論理・平均とグラフ、9月は倍数と約数|小4・Z会の中学受験コース
8月号「論理」ってどういう内容?/小4・算数
8月号のテーマは1回目が「論理」、2回目が「平均、グラフ」でした。
算数における「論理」問題とはどんな内容なのか気になったのですが、与えられた条件をもとに筋道を立てて考え、正しい答えを求める問題を指すようです。
たとえば、一番はじめの問題として、「4人が同時に走ったところ、ア 同時にゴールした人はいない、イ ◯さんは□さんの2人前にゴール、ウ △さんよりあとにゴールした人は……」といったような条件がいくつか書かれており、それを元に4人の順位を求める問題がありました。
ほかにもトーナメント戦(条件を元に、どのような組み合わせで勝負したかを考える問題)や投票(何票以上とれば代表に選ばれるかといった問題)もあります。
これらは問題の文章をきちんと読めて理解できているかが焦点となる問題のような気がしました。
8月号の2回目は「平均とグラフ」
8月号2回目のテーマは「平均とグラフ」。
平均はそこまで難しい内容ではないと思います。
グラフは直線や棒グラフ以外の、いろいろな形のものが出てきました。
タクシーの料金や荷物の送料など、一定の水準までは同じ数値である場合のグラフなど、問題としてよく出るかもしれません。
グラフで◯は含まれない、●は含まれるなどの書き方の違いなども覚えておくと良さそうです。
9月号「倍数と約数」+ベン図/小4・算数
9月号は倍数と約数がテーマですが、まずはベン図から学びます。
ベン図自体は過去でも学習したことがありますが、今までは2つの条件が多かった気がします。
今回から3つ以上の条件が出てくるので、ベン図を書くときに文字や線が重なって、読みづらくならないよう注意が必要です。
そして倍数、最小公倍数の登場です。さらに約数と最大公約数も続けて学びます。
まずは基本のやり方を習ってから、素因数分解のやり方と、それを使って最大公約数、最小公倍数を求める方法を学びます。
素因数分解のやり方は、単純なしくみなのでわかりやすいです。
一番の課題は、文章題を読んで、これは最小公倍数、最大公約数を使う問題かどうかを見極められるかどうかだと感じました。
練習問題では、とある長方形を同じ向きに重ならないように並べて、正方形を作るときの問題や、大きな長方形の紙に正方形の色紙を敷き詰めた場合の正方形の辺の長さなどを求める問題があります。
このとき、なぜ最小公倍数を使うのか、どのような問いの場合は最大公約数を使うのか、根本を理解していないと、すこし文章が変わっただけでミスを起こしそうです。逆に根本さえ理解できていれば、多少の計算ミスは現段階では問題ないように感じました。
理科/8月は温まり方とかさ、9月はてこと天秤など|小4・Z会の中学受験コース
8月号。温まり方や、かさは普段目にする事象/小4・理科
8月号の理科は温度に基づいたテーマでした。
空気、水、金属について、温度が変わるとどのような変化があるのかを学びます。
また、金属を温めたときの温まり方(伝導)についても詳しく書かれていました。
大人から見ると熱の移動の説明箇所はわかりきった内容のように感じました。
子供からすると考えたこともない事象だと思うので、読み物として読んでおくだけでも学習の効果があるのかもしれません。
-

-
七田式の社会科・理科ソング【購入】歌の力で無理なく記憶!?
こんにちは、とはのです。 すっかり間が空いてしまいましたが、その間に学習・勉強系のグッズや習い事が増えました。 いくつか良かったものがあるので、今回はその中のひ ...
続きを見る
9月はてこと天秤、ものの燃え方と空気/小4・理科
9月号ではてこについて触れています。
てこについては七田式CDはもちろんのこと、理科系の学習まんがを買うとたいてい載っている分野なので、わかりやすいと思います。
どこが力点・支点・作用点なのか、位置によって力はどう変化するかを抑えておけば難しくはなさそうです。
そのほか「ものの燃え方と空気」についても学習しました。
ものが燃えるには、酸素が重要であるということをわかっているお子さんは多いと思いますが、それを証明するのは難しいはずです。
たとえば「ものを燃やしている空間を密閉して空気を遮断すれば、火は消える。空気を入れれば、ものが燃えたまま。だから酸素が重要、つまりものを燃やす性質がある。」これだとNGです。空気には酸素以外の気体(窒素など)も含まれているため、酸素ではなく窒素がものを燃やす性質がある可能性があるからです。
Z会では空気のなかには窒素およそ78%、酸素およそ21%、そのほかの気体がおよそ1%であることを説明したうえで、実験を重ね、結果「酸素」がそのはたらきを持つことを証明していました。
さらに燃えたあとの空気の変化についても解説がありました。
石灰水を使った解説もあるので、石灰水の特性を知っておくのも重要なポイントとなります。
先ほどの酸素がものを燃やす性質があることを証明する際の実験では、二酸化マンガンやオキシドールを使っていたので、これらの性質や実験方法もあわせて覚えておくと良さそうです。
社会/8月は低地・高地の暮らし。9月は日本の気候がテーマ|小4・Z会の中学受験コース
社会は8月号も9月号も…暗記!暗記です。
8月号では日本の川、平野、山地や湖の名称と位置。輪中地域の名称と説明、中央高地の名称と説明が中心。
9月号では気団、海流の種類と説明。盆地の名称と各都市の雨温図を学びます。
名称のほとんどが漢字であり、さらに難しい漢字も多いので、漢字だらけのテキストに読む気がなくなるかもしれません。
理解よりも暗記がものをいう範囲だなと感じました。
前回の7月号同様、平野や川、山などの名称と位置など、覚えることがたくさんです。
-

-
Z会中学受験コース・小学4年生6~7月号/社会は漢字に苦戦?
こんにちは、とはのです。 今回はZ会の中学受験コース・小学4年生の6月号・7月号についてです。 すこし駆け足記事ですが、気になる方はご参考ください。 過去のZ会 ...
続きを見る
社会については新しいことを覚えたというよりも、「覚えないとおかないといけない試験範囲の資料」をもらったといったイメージでした。
私感として、8月9月については算数と理科が内容的に良かったです。
国語や社会の内容も悪いわけではないですが、Z会ならではの良問というよりかは受験で抑えておきたい問題集を読んだといった印象でした。
以上、中学受験コース・小学4年の8月号・9月号の内容の話でした。どなたかのご参考になればと思います。