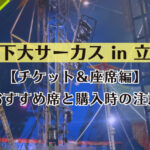こんにちは、とはのです。
今回はZ会の中学受験コース・小学4年生の6月号・7月号についてです。
すこし駆け足記事ですが、気になる方はご参考ください。
-

-
Z会中学受験コース・小学4年生の2~3月号。小数/植物/市…
こんにちは、とはのです。 今回はZ会・中学受験コースの小学4年生2月号・3月号について。 小学4年生については、以前、前半期と後半期で分けてざっと書いたのですが ...
続きを見る
過去のZ会の記事は、「Z会の記事一覧」をご確認ください。
国語/6月は詩。7月は場面や気持ちの移り変わり|小4・Z会の中学受験コース
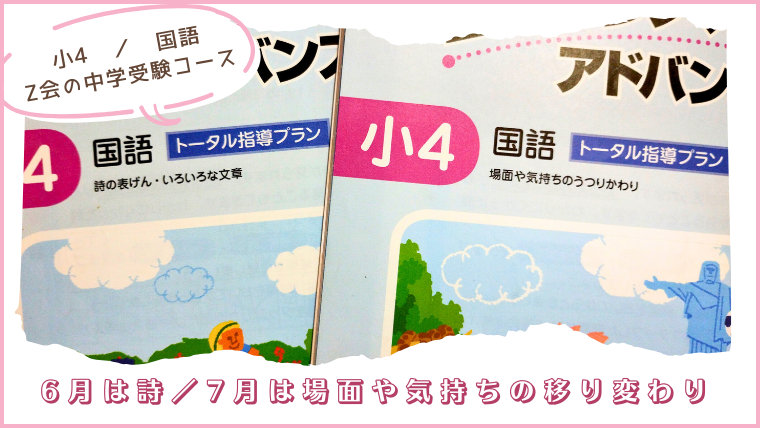
Z会・中学受験コース小4の国語6月号は「詩」。7月号は「場面や気持ちの移り変わり」がテーマでした。
6月号では「詩の表現方法」を確認/小4・国語
国語・6月号では詩の表現方法を最初に学びます。たとえば比喩や擬人法ですね。そのほか6つの表現方法を学びます。
また、さまざまな文章形態に関しても簡単な説明がありました。随筆文、記録文、伝記文、戯曲や脚本などです。随筆や記録文については、読み取るときのポイントも書いてありました。
今回は詩がテーマということもあって、文章題でも詩を取り扱った練習問題も2つ用意されていました。
詩はほかの文章に比べて短いものの、言葉のすべてに思いや考えが込められているものが多く、かつ明確に「こう」とは書かれていません。そのため、詩が文章題だったときは、詩に含まれるメッセージをどう拾いあげ広げていくか、どう言葉にできるかが肝のような気がします。
7月号は「場面や気持ちの移り変わり」/小4・国語
国語の7月号では、場面や気持ちの移り変わりがテーマでした。
ただ、このあたりはいままでの文章題でも無意識にくみ取れていたであろう部分なので、あえていまテーマとしておく必要があるのかと若干疑問にも感じました。
文章題については、前回にくらべて長い文章がいくつもあったせいか、子供自体が忙しくてやる気がでなかったのか、空欄が目立っていました。
その証拠に空欄の箇所に答えを書き込んでいなかったり、漢字の練習を抜かしていたりしていました…
漢字はZ会も力を入れている
子供はサボリ気味の漢字ですが、Z会は毎号漢字の練習問題のためのページ数をそれなりに確保しています。筆順や二字熟語の関係性の問題などが出てくることもあって、それだけ漢字が受験において重要なポイントであることがうかがえます。
算数/6月は多角形、7月は合同と対象・分数|小4・Z会の中学受験コース
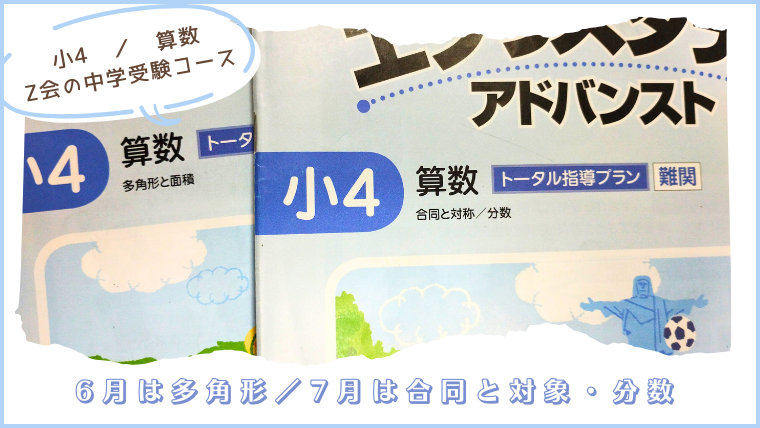
Z会・中学受験コース小4の算数6月号は「多角形と面積」。7月号は「合同と対象/分数」がテーマでした。
6月号では多角形の角度や面積の求め方/小4・算数
6月号の算数は多角形の角度の求め方を学びました。
多角形の内角の和は「頂点の数ー2」で求められます。
式だけを覚えてしまいがちですが、ここではまずは式を使わず持っている知識のみでどうすれば内角の和を求められるかを考える方法を学び、その後「頂点の数ー2」の式が適用できることを解説する流れが組まれていました。
内角の和にかぎらず、Z会は基本的に式を使わずに解く方法や概念を教えてから、結果的にこうした式が使えるという流れをとるので、式だけの記憶力ではなく考え方の応用力を養う勉強だと感じます。
それらをもとにさまざまな図形の角度の求め方を練習します。よくテストで見かける星型など代表的な問題も多かったように感じました。
続いて面積の求め方です。
平行四辺形・三角形・台形・ひし形などの面積を求めます。
これらも公式を教える前に考えさせる問題があって、その結果、こうした公式が成り立つといった流れで解説が進んでいます。このあたりは落ち着いて考えれば解ける問題が多いと思いました。
ただ、多角形の角度や面積は、中学、高校と今後もずっと関わっていく単元であることを考えると、今号はその基礎の基礎。重要なテーマだったと感じます。
7月号では合同と対象・分数/小4・算数
算数と国語は毎号2つずつテーマとテストがあります。
7月号ではまず1回目のテーマとして「合同と対象」を学びます。
中学では仮定と証明がありますが、それほど深いことは学ばず、小学校の現段階では単純に「大きさも形も同じでピッタリ重ね合わせたら合同」と説明しています。
- 複数ある画像のどれとどれが合同なのか
- 折った図形のどの部分とどの部分が合同であるか
- 合同であるからこそ、どこの線の長さと角度が同じであるか
こうしたことを理解・練習していきます。
また、点対称や線対称も実際に書く練習をしました。
図形問題は空間認識能力が問われるので、そのあたりが備わっていないと時間がかかるかもしれません。
この段階では立方体・展開図などは出てきていないので、その段階に行く前に平面をしっかり把握しておく必要があるように思いました。
2回目テーマは「分数」です。仮分数と帯分数、そして分数から小数、小数から分数に直す方法を学びます。
そこまで難しい内容ではないので、仮分数から帯分数、帯分数から仮分数、分数から小数にするときなど、計算ミスがないようにすれば問題ないかと思います。
理科/6月は天体、7月は水と地層|小4・Z会の中学受験コース

小4・理科の6月号は天体に関すること、7月号は水と地層を学びます。
6月号では「太陽・星・月」の動き/小4・理科
6月号では天体について学びます。
星の等級、代表的な星座や動きなど。小4ではおそらく学校でも天体観測など学習し、夏では夏の大三角形、冬にはオリオン座が時間ごとにどう動くのかを観察する宿題が出る場合もあります。そのあたりの予習にもなると思われる範囲でした。
また、太陽・陽の時間ごとの動きや月の満ち欠けについても学びました。
小4の段階ではそこまで難しい考え方が出てくるわけではありません。たとえば虫眼鏡で光を集めるとどうなるか、日なたと日かげの温度差など、一般的に知っている内容を言語化・証明・解説しているような構成に見受けられました。
7月号は水の変化や地層(大地)/小4・理科
7月号は水の変化→川の流れ→地層の様子などを学びました。
水については、温めるとどうなるか、湯気の様子、凍るタイミングやかさの変化などを学びます。
普段料理のお手伝いなどしていれば、目にすることも多いであろう事象なので、それと絡めて学ぶとイメージしやすいかもしれません。
続いて自然界の水・川の動きについて学びます。
土山を作ってホースで水を流してみようという実験が載っていて、調べてみると、小学5年生の「流れる水のはたらき」で学習する内容のようです。
ご家庭での実験が難しい場合は、NHK for School を参考にされると良いかもしれません。水の働きや動きを実験した映像がいくつかあります。
【参考サイト】
川の流れ関連で地層や堆積岩についても学びます。
堆積岩の名前を覚えるのはすこし大変ですが、地層からなにが読み取れるかについては理解しやすいかと思われます。
水の変化・地層ともに、7月号の理科は比較的イメージしやすい内容のため、月例テストでは点数が普段以上に取れるお子さんが多いかもしれません。
社会/6月は中部~北海道地方、7月は日本の地形|小4・Z会の中学受験コース
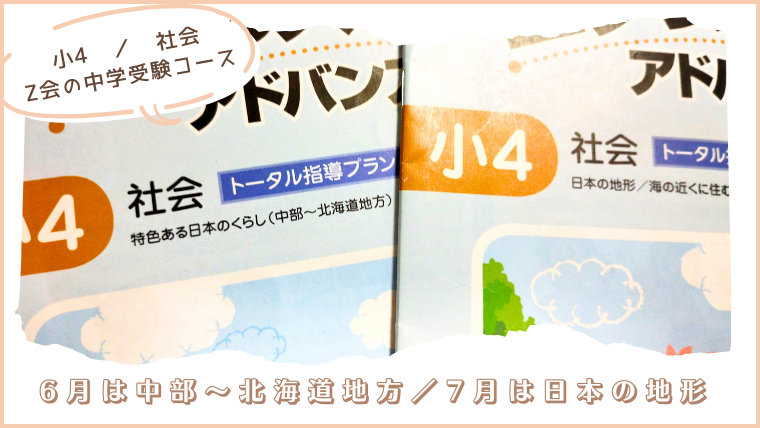
小4・社会の6月号は中部~北海道地方、7月号は日本の地形に焦点をあてたテーマでした。
6月号は中部・関東・東北・北海道/小4・社会
前回の5月号が九州・近畿地方中心だったので、今回はその続きといった印象。
中部・関東・東北・北海道と、範囲が広いわりに1冊にまとめられているので、それぞれの都道府県の特色のなかから、とくに重要事項・中学受験でおさえるべき内容のみをまとめて紹介しているような印象を受けました。
難関校以上の学校が志望校の場合は、これだけの知識では足りず、来年度以降の社会でより一層掘り下げていく必要があります。
中学受験コースの理科も社会も、小5から一気に内容が広範囲かつ深い内容になるので、今回の部分は余裕があるうちに暗記しておいたほうが良さそうです。
7月号は日本の地形、海の近くにすむ人々のくらし/小4・社会
7月号では、日本の周りの大陸や海流の名称のほか、日本という土地柄に関することを学びます。
たとえば、日本は火山大国でもあり、地震大国でもあり、災害だけでなく恩恵も受けていることにも触れました。
また、半島や湾、島の名称も一気に紹介されていますが、地名・名称は漢字が複雑なものが多く、位置とともに漢字を覚えることに苦労しそうです。
普段目に入りやすい場所に地図ポスターを貼るなどして、スキマ時間に覚えていくのが良いかもしれませんね。
ちなみにわが家にあるのは「小学中学年 学習日本地図 (キッズレッスン 学習ポスター)」。今回Z会で習った内容がすべて入っているというわけではないですが、中学年の学習指導要領に準拠していて、伝統工芸品や特産品、三大急流や三大湾などおさえておきたいポイントもほどよく入っているのでおすすめです。
紙も大きくてしっかりしていますよ。
より情報が深い高学年用のポスター「小学高学年 学習日本地図 (キッズレッスン 学習ポスター)」もあります。
他社のものとも比べながら、ひとつご購入されてみては。
毎回駆け足気味の記事ですが、以上、中学受験コース・小学4年の6月号・7月号の内容の話でした。
どなたかのご参考になればと思います。