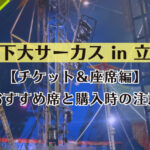こんにちは、とはのです。
前回に続いて、Z会の中学受験コース・小学4年生についてまとめます。
今回は4月号・5月号についてです。すでに子供が上の学年になってしまったためかなりの駆け足記事ですが、気になる方はご参考ください。
-

-
Z会中学受験コース・小学4年生の2~3月号。小数/植物/市…
こんにちは、とはのです。 今回はZ会・中学受験コースの小学4年生2月号・3月号について。 小学4年生については、以前、前半期と後半期で分けてざっと書いたのですが ...
続きを見る
過去のZ会の記事は、「Z会の記事一覧」をご参照ください。
国語/品詞や接続語|小4・Z会の中学受験コース
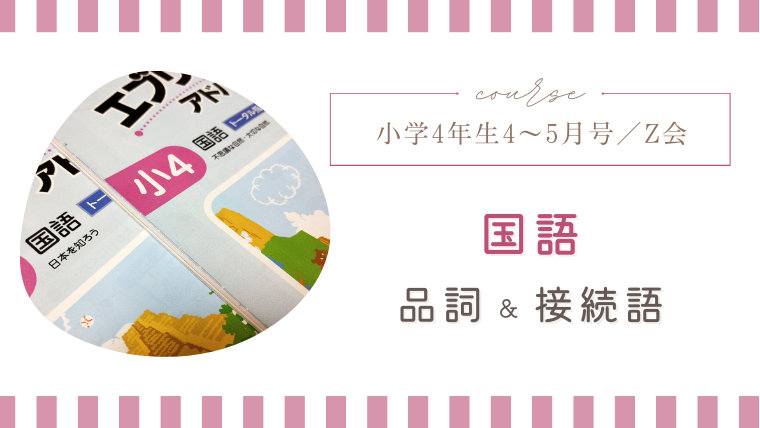
国語は2月号と3月号と違い、4月号と5月号との間にはとくにつながりはありませんでした。
「言葉の学習」4月号は中学で習う内容?
4月号の言葉の学習は「名詞・動詞・形容詞・形容動詞」。
名詞以外の形の変化について解説する部分もありました。
形容詞と形容動詞の形の変化は、私自身、過去に「未然、連用、終止、連体、仮定、命令」の形を覚えさせられた記憶があります。
ここでは「未然、連用、終止、連体、仮定、命令」の名前自体は出てきていませんが、パターンについてすこしだけ解説していました。
解説はやや不十分の印象
「すこしだけ解説」と書いたとおり、形容詞と形容動詞の形の変化についてはサッとしか説明されていません。
形容動詞は物事の様子を表す言葉であり、動詞・形容詞・形容動詞は下に続く言葉によってこんなふうに形が変わるよといった解説のみにとどめています。
そのため、これだけで理解するのはすこし厳しい気がするし、Z会にしてはすこし中途半端な説明の仕方である印象を受けました。
「言葉の学習」5月号は組みになって使われる言葉と接続語
5月号の言葉の学習は「組みになって使われる言葉」と「接続語」でした。
組になって使われる言葉は、たとえば「もし~」という言葉がきた場合は、「なら(たら)」という言葉が後に続きます。
そうした組み合わせの言葉を紹介していました。
接続語はいままでにも習ったことがあると思うので、そこまで苦戦はしないと思います。
国語の文章題
文章題は4月号が自然のテーマ、5月号は日本に関することがテーマでした。
国語については特筆する点はないですが、だからといって国語を受講する必要がないというわけではありません。
それなりのレベルのワーク・映像授業を受けられる点がメリットだと思うので、毎月のワークをこなす→毎日練習ブックの漢字・練習問題をくり返すだけでも、それなりに力がつくような気がします。
算数/線分図・数列、垂直・並行|小4・Z会の中学受験コース
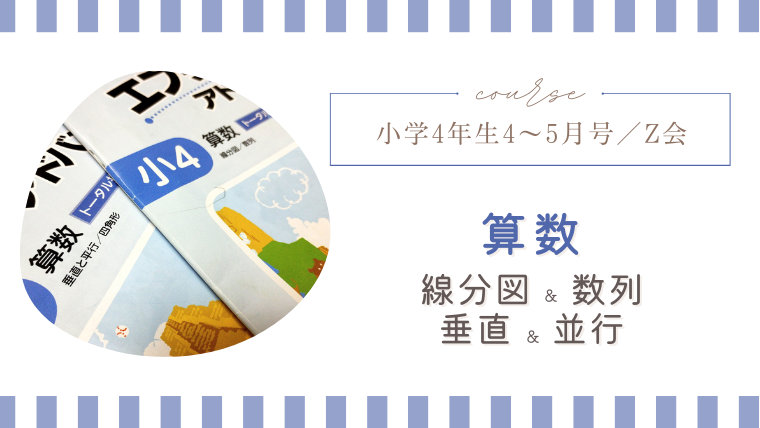
Z会の小4・4月号の算数は「線分図/数列」、5月号は「垂直と並行/四角形」でした。
4月号の算数「線分図/数列」…見覚えあり
まずは線分図。
これはハイレベ100(小2)やトップクラス問題集(小1)で似たような問題が出てきています。そのため、そこがクリアできてれば、難しいことはなさそうですが、第一子はハイレベ100に苦戦していたので、ここでもつまづくことがありました。
-

-
【ハイレベ100】小学1年の算数と読解力。失敗と相性/ブログ
こんにちは、とはのです。 今回は市販の教材「ハイレベ100」シリーズについて、小学校1年生のときに使ったものを中心にお伝えします。 今回紹介すること Z会と併用 ...
続きを見る
おそらく取り組んだ記憶がないと思われます…。
続いて「周期算」。
数字のくり返しがある計算を「周期算」っていうんですね。知りませんでした。小4では「わり算の商とあまり」を使って答えを導き出す方法を学びます。
その次は「日暦算(にちれきざん)」。
「1月10日の◯日後は何月何日ですか」「◯月◯日~□月□日までは何日間ありますか」といった問題です。日暦算は下の学年でも出てきました。第二子が取り組んでいた市販教材でヘルプで何回か呼ばれた記憶があります。
そして最後に「等差数列(とうさすうれつ)」。
これも下の学年の…第二子が…。
見返して思ったのですが、どれもこれも下の学年の市販問題集で似た問題が出てきています。
あのあたりの問題が解けているお子さんであれば、苦戦しないかもしれませんね。
ちなみに日暦算は「にしむくさむらい」で31日までない月を覚えておくと便利です。
第二子は小2で最レベ(ハイレベ100内にある「最レベ」レベル問題ばかりのもの)とトップクラス問題集の小1(小1でも難しい)を取り組んでいるので、第二子はそこまでつまづかない気がしますが…はたして
5月号の算数「垂直と並行/四角形」
5月号の算数は「垂直と並行/四角形」でした。
「長方形の紙をおって、この角度は何度?」といった錯角・同位角を使った問題が多いです。
どこか並行で、移動前はどこの角度だったかなどに気づければ解けるかと思います。まだ習い始めの単元のため、そこまで凝った問題は出ていないようです。
「平行四辺形」の単元では、1つの頂点が結ばれた2辺だけが書かれていて、コンパスや三角定規を使って平行四辺形を完成させる練習問題がありました。
分度器を使わない平行四辺形を作図は意外に知らないと思うので、良い練習問題だと思います。
あとは、台形とひし形、角度の関係を習います。
内角の和や平行などがポイントとなってくるので、このあたりしっかり身につけておきたい単元ですね。
理科/動物の成長|小4・Z会の中学受験コース
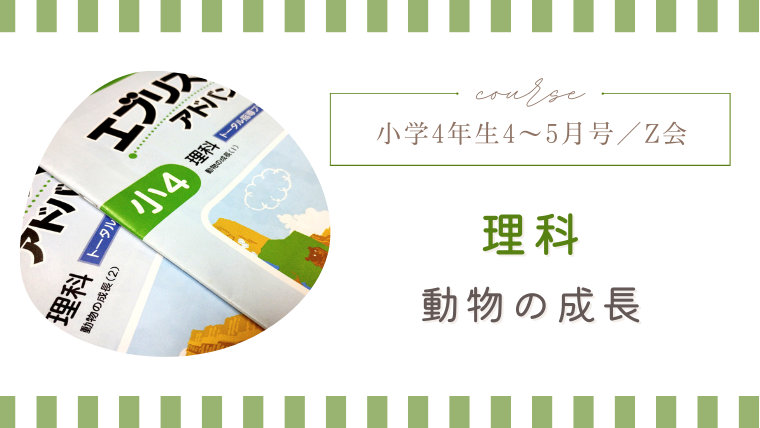
Z会の小4・4月号の理科は「動物の成長(1)」、5月号は「動物の成長(2)」でした。
同じテーマであるものの、内容は以下のような違いがあります。
4月号の理科「動物の成長(1)」では昆虫や魚類が中心
4月号の理科は昆虫や魚類についての解説が多かったです。
たとえば完全変態や不完全変態について、昆虫の種類ごとの季節の過ごし方、あとはメダカの育ち方など。
メダカの育ち方は有名ですね、身近な生物かつわかりやすい成長の変化を見ることができるので、題材としてもよく出てくるのかもしれません。
そのほか、人の誕生についても軽く説明されていました。男性と女性の体の違いと受精~胎児の成長の様子までに触れています。
5月号の理科「動物の成長(2)」は人体が中心
5月号では人体を中心とした内容になっていました。
人体の動き(呼吸・血液・消化)など。そのほかに、人と外界(自然・食物・水)との関わりなども解説していました。
理科の4月・5月は総じて「生物」のテーマでまとめられていました。
内容としては身近なものが多いので難しくはありませんが、どっちがどうだったっけ?と混乱しそうな内容(静脈・動脈・血液の流れ、メダカのオスメスの判別方法)なども多いので、受験を意識するならばそのあたりを重点的に覚えていく必要がありそうです。
社会/地図と都道府県|小4・Z会の中学受験コース
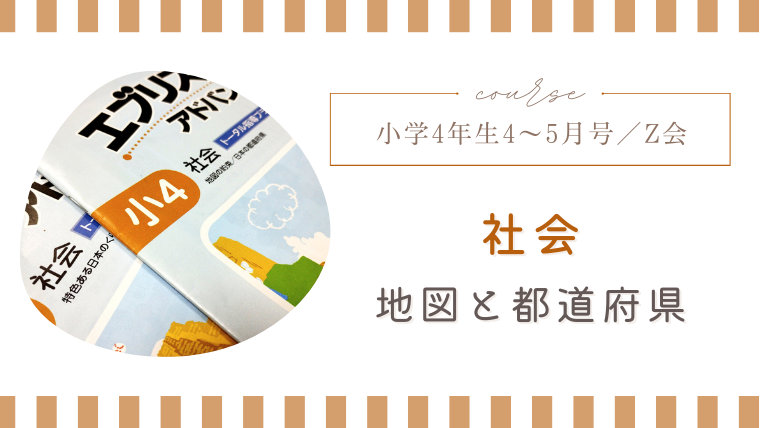
Z会の小4・4月号の社会は「地図の約束/日本の都道府県」、5月号は「特色のある日本のくらし(九州~近畿地方)」でした。
同じテーマであるものの、内容は以下のような違いがあります。
4月号の社会は地図記号と日本について
4月号は地図の見方、方角、地図記号が前半で、後半は日本国全体のことを解説していました。
たとえば、都道府県の形、政令指定都市や海に囲まれている道県、内陸県、人口の多い・少ない県についても触れています。
都道府県については、地図ポスターや学習まんがなども活用されると良いかもしれません。地図ポスターについては、以下でも紹介しています。
-
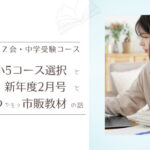
-
Z会・中学受験コース小5のコース選択と2月号。役立つ市販教材
こんにちは、とはのです。 2回にわたってZ会・中学受験コースの小4について所感をお伝えしました。 今回は文字数の関係上、書ききれなかった補足(役立ちそうな市販の ...
続きを見る
ちなみに、「るるぶ 都道府県いちばんかるた」もかなりおすすめです。下の子も楽しく遊べたので、小学校低学年から取り入れても良いと思います。
5月号の社会は九州・近畿地方中心
5月号の社会は、九州地方から近畿地方の特色について触れています。
九州はシリコンアイランドと呼ばれていることと理由、四国地方の気候や本州とのルート、各県の地域産業・特徴などが解説されていました。
また、促成栽培や近郊農業の言葉の意味とそれをおこなう地域、日本の時間の基準点はどこかといった内容もありました。
今回社会で習ったことは、国語の漢字や算数の計算のようにくり返すものでもなく、理科のように身近なテーマでもありません。
意識しないと触れない情報ばかりなので、くり返しテキストの問題を解いて暗記していかないと、わが家のように翌年以降記憶にすら残らない可能性があるかと思われます。